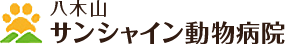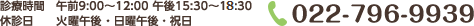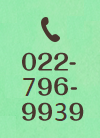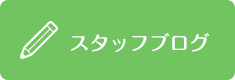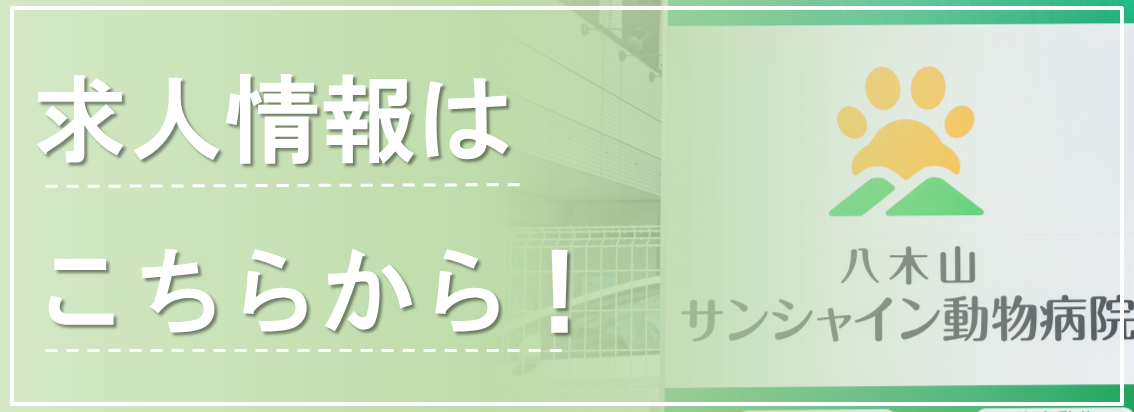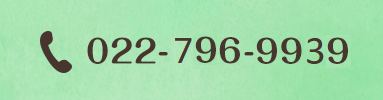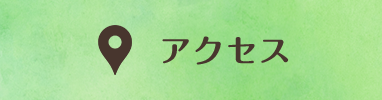犬・猫の熱中症について
今年の夏は例年より特に暑いということで夏バテされている方もいらっしゃるのではないでしょうか?
動物も人と同じように暑さで体調を崩すことがよくあります。
今回はわんちゃん、ねこちゃんの熱中症についてお話したいと思います。
熱中症とは 高温・多湿な環境が原因で体温が上がることにより生じる疾患です。対応が遅れると脳や内臓に機能障害がでる可能性もあり、最悪の場合は亡くなることもあります。
主な症状 初期 ・呼吸がいつもより荒い(ねこちゃんが口を開けて呼吸している。)
・よだれが多い
・元気がない
悪化すると ・嘔吐、下痢
・発作
・意識がない
・体に力が入らない
このような症状が出た際は速やかに体を冷やしてあげてください。
・涼しい場所に移動させる。
・全身に水をかけて、風を当てて冷やす。
・濡らしたタオルまたはタオルで包んだ保冷剤で体を冷やす。
※体を冷やす際は太い血管が通っている場所→首(喉側)、脇の下、内股を冷やすとより効果的です。
熱中症対策 ・室内はエアコンを使用して適度な温度・湿度を保つ。(温度25℃〜27℃くらい)(湿度45%〜65%くらい)
・短時間でも短時間でも風通しの悪い室内や締め切った車内での留守番は控える。
・わんちゃんの散歩は涼しい時間帯(早朝や夜)に行く。
他にも室内に冷感マットを敷いたり、散歩中に首に保冷剤を巻くなどの対策も効果的です。

また、犬ではパグやブルドッグ、猫ではペルシャやヒマラヤンなどの短頭種は熱中症のリスクが高くなります。種類に関係なく幼齢・高齢の子、肥満や心疾患のある子も特に注意が必要です。
わんちゃん、ねこちゃんの様子がいつもと違うと感じたら早めの受診をおすすめします。
まだまだ暑い日が続くと思いますので、熱中症対策をしっかりして夏を乗り切りましょう。
気分転換に🐾
昨日は休診だったせいか花音が少し元気がなかったので、気晴らしにお散歩へ行きました。
暑かったので本当は連れて行きたくなかったのですが、日陰を探しながら歩きました。

今日はもういつもの花音にもどっていました(╹◡╹)
犬のアトピー性皮膚炎
犬のアトピー性皮膚炎は何らかの刺激に体が過剰に反応し、皮膚が痒くなる病気です。アレルギーが原因の一つなので他の犬にはうつりません。
遺伝的素因があるといわれており、柴犬、シーズー、フレンチブルドッグ、トイプードル、G・レトリーバーなどに多くみられます。
比較的若い、生後6ヶ月〜3歳くらいから症状が出始め年齢を重ねるごとに痒みがひどくなる傾向にあります。完治は難しいといわれており生涯にわたりアトピー体質と上手に向き合い、付き合うことが何よりも重要です。
治療には症状を緩和するための薬物療法、スキンケアなどを組み合わせて行います。
薬物療法…痒みが強い場合はステロイド剤の使用が効果的ですが副作用が強いため長期的に使用はできません。そのため当院では安全性が高く比較的長期服用も可能なオクラシチニブ剤やシクロスポリン製剤も使用しています。その他、痒みを持続的に緩和することができる抗体医薬があります。これは一回の注射で約1ヶ月間症状を緩和することができるというものですが、全てのわんちゃんに効果があるというわけではありません。
スキンケア…本来皮膚にはバリア機能がありアレルギー物質を含む様々な刺激が入ってこないようになっています。しかしアトピー性皮膚炎を患う犬の皮膚はこのバリア機能が低下しているため、アレルギー物質が体内に入り込んでしまい痒みを引き起こすのです。そのため低刺激または保湿作用の強いシャンプーを使うとともに、保湿剤を使用してスキンケアをすることで皮膚バリア機能を助けることができます。
皮膚用のドッグフード…健康な皮膚を維持するためのオメガ脂肪酸などを豊富に含んだフードなどを取り入れると、薬の量や頻度を減らすことができるといった治療補助効果が期待できることがあります。
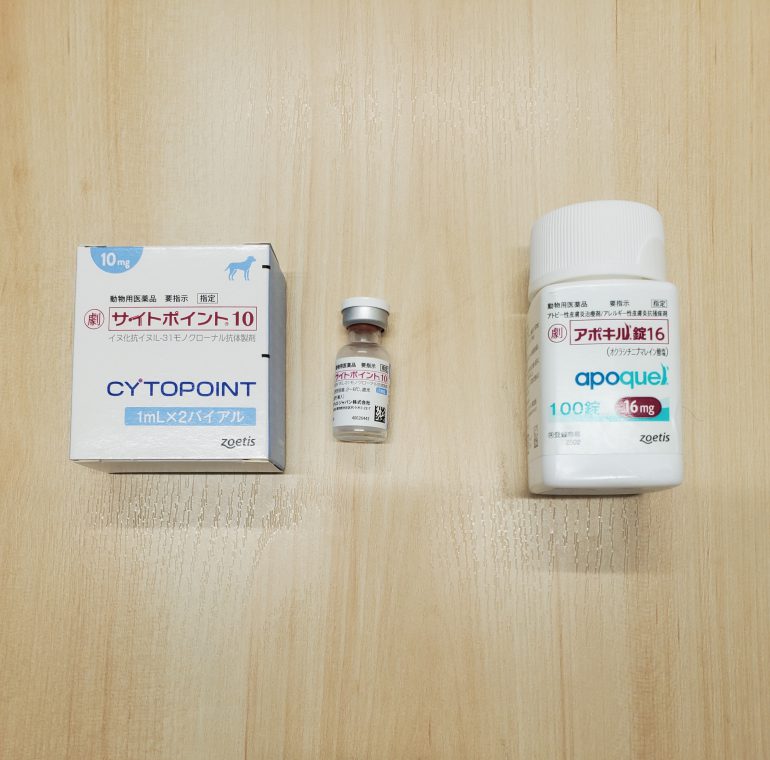


アトピー性皮膚炎と診断されたら皮膚を清潔に保ち、なるべく環境からの刺激を受けないように気をつけてあげましょう。

犬の膝蓋骨脱臼について
今回は犬で特に多い病気「膝蓋骨脱臼」についてお話しします。少しでも病気について知ることで知識を広げ、愛犬・知り合いのわんちゃんが病気にかかったときすぐ対応できるようこのお話しを読んでいただけたら幸いです。
◦膝蓋骨脱臼とは?
脱臼は関節のある部位であればどこでも起こる可能性がありますが、中でも犬に多いのが「膝蓋骨脱臼(パテラ)」です。膝蓋骨とは一般的に「膝のお皿」と呼ばれる部位のことです。通常は大腿骨内にある「滑車骨」というくぼみにはまっているのですが、その溝から膝蓋骨が外れた状態を「膝蓋骨脱臼」と言い膝蓋骨が内側に外れると「内方脱臼」で外側に外れることを「外方脱臼」といいます。
「膝蓋骨脱臼」の症例は外方脱臼よりも内方脱臼の方が多く見られます。内方脱臼はトイプードル・チワワ・ポメラニアンなどの小型犬で、外方脱臼は大型犬で多く見られる傾向があります。
◦原因
「外傷性」と「先天性」があり外傷性は交通事故・高いところからの飛び降り・転倒などが原因で起こります。先天性の場合は生まれつき膝関節の筋肉や靭帯に異常があること原因で子犬の時から発症していることもあれば、発育に伴って発症することもあります。
◦症状(4つに分けられる「グレード」)
グレードI:普段は無症状だが時々症状が出る。日常生活にあまり支障がない。
グレードII:時々足を浮かせて歩いているが曲げ伸ばしすると簡単に整復される。日常生活にあまり支障はない。
グレードⅢ:常に脱臼している状態だが整復することが可能。足を引きずる・しゃがんだ姿勢で歩くなどの症状が出る。
グレードⅣ:常に脱臼していて整復することが不可能。骨が変形し膝を曲げた状態で歩いたり、全く歩けない状態になることもある。
グレードⅡまでは症状が軽いため飼い主さんが脱臼に気づかないこともありますが、小さな脱臼が繰り返し起こることで関節に炎症が起こり関節炎につながることもあります。また痛めた足を庇って歩くことで反対側の足に負担がかかり症状が更に悪化していくこともあります。立っている時に関節がガクガクする・足を引きずることがある・遊んでいるときに急に鳴いて痛がりだしたなどの症状があります。
◦治療
内科治療:内服薬やサプリメントなどです。合わせて運動制限や体重制限などの指示があります。
外科治療:「骨組織の再建術」と「軟部組織の再建術」の大きく2種類があります。
内科治療を行うのか外科治療を行うのかについては脱臼のグレードや犬種・年齢などによって判断します。
◦予防
先天性の膝蓋骨は防ぐことは出来ませんが、負担をかけないよう生活することで悪化を防ぐことができます。
生活環境としては、段差や階段のない道を歩くようにする・フローリングなどの硬くて滑りやすい床にはカーペットを敷くなどの工夫で膝への負担を軽くできます。また体重が増えすぎると膝への負担が増すので体重管理も重要です。
◦愛犬の体に負担がかからないように生活環境を見直し、もし何か症状や気になることがあった場合動物病院へ受診で、愛犬の体を守ってあげましょう。
お散歩🐾
昨日はまたひより台大橋をお散歩しました。
大橋の下の道路へ行ける階段があったので下りてみました。
意外と長い階段で、大橋をダッシュしていた令音には(上に戻る)上り階段はきつそうで、帰り道は背中を丸め疲れきっていました。




花音は10歳ですが、足取りはまだまだ若く令音には負けていません💪🏻
爪切り🐱
爪が伸びてきたので切っているところをパシャリ📸


ハイハオは爪切りが苦手ですが、今回はお利口さんでした💮
とら吉はいつも通りお利口さんで、カメラを構えたらセクシーな写真が撮れてしまいました😳
膵炎について
今月は膵炎についてお話していきます。
まず膵臓は、トリプシンなどの消化酵素を十二指腸に分泌しています。正常な状態では、消化酵素は膵臓内で不活性な状態で存在し、腸内に分泌されてから活性化しますが、何らかの原因により膵臓内で活性化されてしまい、膵臓自体を消化してしまうことで膵臓に炎症が生じることを膵炎といいます。発熱や元気食欲の低下、嘔吐や下痢、脱水症状などを示し、最悪亡くなってしまうケースもあります。これが急性膵炎です。また、この急性膵炎と似た症状が断続的に起こるのが慢性膵炎です。
《要因》
はっきりとした原因はわかっていませんが、いくつかの要因はあげられます。
①高グリセリド血症(中性脂肪)の犬
②ゴミや残飯、食卓上の食べ物を食べてしまった場合
③脂肪を多く含む食事や肥満な子
特に③のケースが多くみられます。また、クッシング症候群や糖尿病、甲状腺機能低下症などの内分泌疾を持つ子が膵炎になるリスクが高まるといわれています。
《当院での検査》
・血液検査→血液検査でCRP(炎症の数値)と検査キッドで膵特異的リパーゼを確認。
・レントゲン検査
・超音波検査
《治療》
入院か通院かは飼い主様とご相談してにはなりますが…
・点滴
・制吐剤
・膵炎用注射(ブレンダZ)
・低脂肪食への変更↓

軽症の場合は、皮下点滴や注射、内服薬で様子をみることもあります。ただし急性膵炎は、急激に悪化することも多いため、症状が落ち着かない場合は再度病院へ受診してください。
《予防》
明確にこれが予防法といえるものはありませんが、人間の食べ物、食べ残し、ごみを口にしないよう対策をする。肥満であれば適正体重まで減量をする。
《急性膵炎で起こりうる合併症について》
・急性腎不全
・呼吸困難(肺水腫など)
・ショック症状
・糖尿病
・播種性血管内凝固(※全身の血管内で小さな血栓が作られ血管につまることもある末期的な状態)
などがあげられます。
《慢性膵炎になってしまったら》
食事をきわめて脂肪分の少ない食事に変更することが大切です。膵炎の子におすすめなのが低脂肪のお食事です。何種類かございますのでまずはご相談ください。
白内障について
今回は「白内障」についてお話します。
白内障とは、瞳孔の中にある水晶体というレンズが白灰色に濁り、視力が低下していく病気のことです。
一度濁ってしまったレンズは元には戻りません。症状が進行すると失明する可能性もあります。
また、緑内障などの眼疾患も併発する場合もあります。
猫ちゃんよりもわんちゃんの方が白内障になりやすいそうです。
○症状
主に見られる症状として、「眼の真ん中が白く見える」「物にぶつかる様になった」「名前を呼んでも反応はするがこちらを見ない」などがあります。
○原因
加齢と共に発症しやすくなり、徐々に症状が進行していきます。
また、稀に見られるのが外傷や遺伝が原因で先天性であり、若齢でも起こりうる病気です。
○好発品種
白内障になりやすい犬種として「ダックスフンド」「チワワ」「ヨークシャー・テリア」「トイ・プードル」などが多いそうです。
○検査
主にスリットランプという機器を使用し、眼に光を当て拡大し水晶体が白く濁っているかを診ます。
○治療
「内科的治療」
点眼薬を使用して症状の進行を抑制させます。しかし完治はしません。
「外科的治療」
特殊な機器を使用し、濁ったレンズを人工レンズに置きかえ視力を戻す手術になります。
○手術をする上での注意点
・全身麻酔で長時間に及ぶ手術になる為、高齢の場合は麻酔について充分に理解していただく必要があります。
・術後に人工レンズがうまく入っていない事によるレンズのズレが生じてしまい、視力低下の再発をしてしまう可能性があります。
・一般的な動物病院では手術に必要な機器がない為、眼科を専門に診療している動物病院さんをご紹介する形になります。
○対策
・定期的な健診での早期発見
・眼が白い、充血している、目やにが増えたなど感じたら早めの受診をお勧めします。
・ご自宅でぶつかりそうな危険な物は片付け、家具の配置は極力しない様にし安全に過ごせる環境にしましょう。(目が見えなくなっても、家具の配置を覚えていたりする為)
最近は花粉で痒くなり目を擦ることによって傷が出来、涙や目やにの量が増える場合もあります。
そういう場合も様子を見ずに早めに受診・治療をして悪化を防ぎましょう。